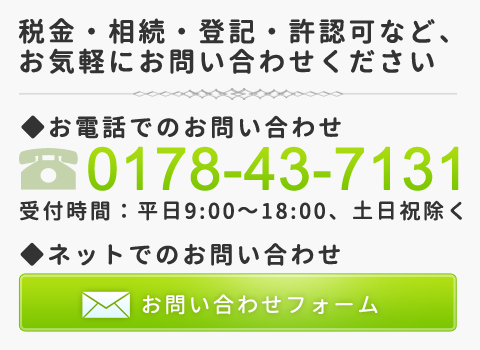週に2~3冊のペースで本を読みます。(ビジネス書中心)
自分は本を読むのがメチャクチャ早いです。
150ページの本なら1時間くらい。
理由はあまり考えないから。ばーっと読んで終わりです。
いいな、と思ったところは線を引いたりページを折ったりします。
でも大抵そのまま。2回読む本はほとんどありません。
それはあまりにもったいないので、今日から書評(感想?)を書くことにしました。
備忘の意味で…。
評価のポイントはひとつで、「商売に使えるかどうか?」です。
対象はちょっと前に出版された本です。
毎日のように新刊がでるのでいい本も埋もれてしまうことがあるので。
なにより古本が安い(笑)
1冊目は2012年発刊の「経営学を『使える武器』にする」(高山信彦)です。
感想は☆☆☆(3点満点)。
経営において、いうまでもなく人材育成はとても重要です。
経営者目線で課題を考え、現場に落としこむ「自走式人材」はどの組織にも必要でしょう。
本書は経営を俯瞰して行動する幹部候補をつくる方法を具体的に解説しています。
著者は人材育成研修を専門にする経営コンサルタントです。
みずほFGや東レなど大企業から通年の研修を受注しているそうです。
1人で活動しているのにすごいですね。
いいなと思ったのは常石造船のエピソード。
ばら積みの貨物船(コンテナではなく石炭などをそのまま積むタイプ)は長さや積載量が決まった何タイプかに分かれています。
たとえばパナマ運河を通過できる最大サイズをパナマックスと呼びます。
ギニアにあるカムサに入れる最大サイズの船はカムサマックスと呼びますが、日本の船主には売れませんでした。
当時、日本の港は最大225メートルの船しか入港できないと決まっていました。
カムサマックスの全長は229メートルなので日本では使えないと思われたんですね。
著者は日本では売れないという社員に対し、現場の声を聞く大切さを説きます。
それを聞いた社員は叱られ、葛藤しながらも日本全国の港を歩きます。
そして調査の結果、日本の港の多くは全長229メートルでも入れる仕様になっていることを知ります。「最大225メートル」と決まっていたのは単にそれより大きい船が来なかったからだった、という事実にたどり着くのです!
常石造船はライバルに先がけ、たくさんのカムサマックスを日本の船主に売ることができました。自分が海運会社に勤務していたころ、カムサマックスのことは聞いたことがあったので、裏のエピソードを知って驚きました。
著者は徹底して現場の大切さを説いていて、VOC(voice of customer)を多く収集することを生徒に課します。どんな業種でも顧客の声を聞くことは重要ですね。
ということで、さっそく自分も飛び込み営業に行くことにしました。
よりよいサービスを提供するために、どんな公認会計士・税理士・司法書士が求められているかを知るためです。
依頼も増えてきて動ける時間がなくなりそうなので、今のうちに…。